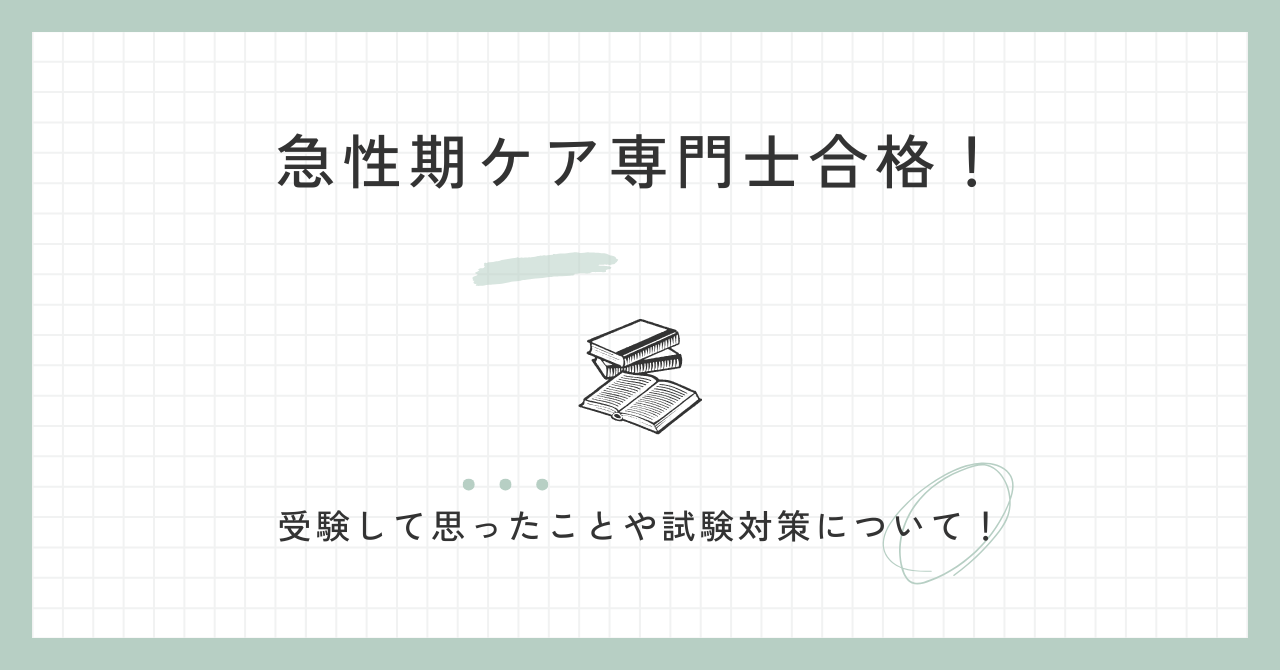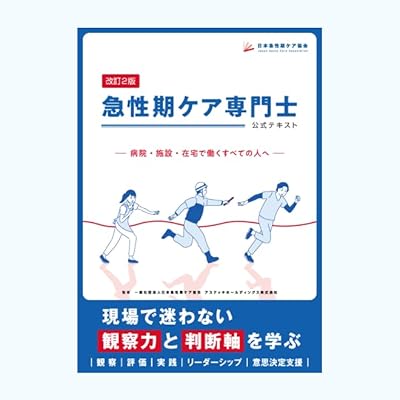このたび5月に第3回急性期ケア専門士試験を受験し合格することができました!
そこで、急性期専門士を取るために勉強してみて、実際にどうだったのか正直に思うことを書いていきます
ネット検索上では、「急性期ケア専門士 意味ない」なんて検索キーワードがあるけど実際はどうなのか…
急性期ケア専門士を取る意味やメリット、実際に行った学習方法やおすすめの試験対策など含めて解説していきます!
急性期ケア専門士を取るかどうか悩んでいる人や、どんな資格なのか興味ある人はぜひ読んでみてください!
 すな
すな急性期ケア専門士を受験してみて実際に感じたことをお伝えします!
急性期ケア専門士とは


急性期ケア専門士とは、日本急性期ケア協会(JACA)が認定する比較的新しい資格で、急変対応や救急医療に関する知識と実践力を体系的に学ぶことを目的とした試験です
・対象者:看護師、医師、薬剤師、臨床工学技士、救急救命士、介護福祉士など、医療介護職で実務経験が2年以上ある方。
・試験形式:90問90分で回答する五肢択一式
・試験範囲:
・急変時の初期対応(BLS/ACLS)
・症状別アセスメント(意識障害、呼吸困難、胸痛など)
・災害医療、家族支援、リーダーシップ
・小児・高齢者の急性期ケアなど
詳しくは別記事にて紹介していますので、詳しく知りたいという方はこちらも参考にしてみてください!


メリット・デメリット


改めてメリットとデメリットをおさらいしていきます
メリット1:急変対応に自信がつく
状態変化の早期発見から初期対応、医師への報告まで体系的に学ぶことができます
今までの経験上、個人的に思うのは急変対応を自信を持って行うには、経験がものをいう部分もあるということ
その経験を重ねていく上で土台になるのが知識だと思うので、その知識を身につけ確実なものにするのが大切です
メリット2:転職やキャリアアップに有利
サイトによっては、転職やキャリアアップに有利と記載してあるところがあります
取得者が少なく希少性があり、急性期病棟やICUなどでの評価が高まる
このように解説している方もいらっしゃるが、本当のところはどうなんだろう?というのが本音です
批判をしているわけではなく、僕自身が「本当に有利になるのかな?」と、疑問に思っている次第です
僕自身が今後、転職する予定なので、実際にどうだったのか要望があれば記事にしてみたいと思います!
メリット3:継続的な学習環境が整っている
資格取得後もオンラインセミナーや研修で最新の知識をアップデートすることができます
資格取得で終わりではなく、医療は日進月歩なので、最新の知識をアップデートできるのは良いところだと思います
気を抜いていると全く勉強しなくなるので、強制的に勉強できる環境を作っておくのはGOOD
メリット4:学習のモチベーションになる
試験という明確な目標があることで、日々の勉強にもハリがでます
目標があることで、学習のモチベーションを上げることができます!
デメリット1:直接的な昇給や診療報酬加算はない
ここからはデメリットについてです
現時点では資格取得による給与アップは期待できません
自己研鑽になってしまいますが、多くの資格は自己研鑽なので、そんなもんかなというのが正直なところ
むしろ給与アップを目的するのなら、認定看護師や専門看護師などを目指すべきかと思います
デメリット2:試験対策がやや大変
範囲が広く、独学では難しい部分もあるため、公式テキストやアプリの活用が推奨されます
後に実際にした勉強対策などをお伝えします!
デメリット3:更新に費用と単位取得が必要
5年ごとの更新にはeラーニング受講料や単位取得が必要です
これはデメリットでありつつ、メリットと捉えるのが良いと思います
強制的に学ぶ機会を作ることで、知識のアップデートが可能です!
実際に受験してみての正直な感想


ここからは、実際に受験してみて正直どうだったのかお伝えしていきます
僕自身は救急に携わってきて10数年が経っているので、それを踏まえての意見なので多少なりとも参考になるかと思います
結論から述べると…
これが正直な感想です
この資格を取ることで、昇給などのメリットはないけど、急性期における知識を総合的に学ぶ良い学習機会になりました
みなさんも急変対応、BLS、ACLSについて学ぶ機会があると思います
しかし、それは単に急変や蘇生行為に対する知識・技術に関しての学びだけど、この急性期ケア専門士は、その知識・技術だけではなく急性期全般における総合的かつ体系的な知識を学ぶことができます
また、蘇生行為に対する知識・技術だけではなく、その時に必要とされるリーダーシップのことなどにも触れられているのは学びの深いものです
急性期全般について学びたい人、急変対応に苦手意識を持っている人にとっては良い学びの機会になるんじゃないかと思います
急性期における急変対応は一場面にすぎず、患者を一貫してみる必要があることを考えると体系的に学べる良い機会でもあるように感じました
医療職者として患者に関わる以上、急変が起こるリスクは避けられないのであれば、受講して知識をつけておくのはアリ!
受けるかどうか迷っているのであれば、それは興味があるということだと思うので、受講してみてもいいんじゃないかと思います!
試験対策
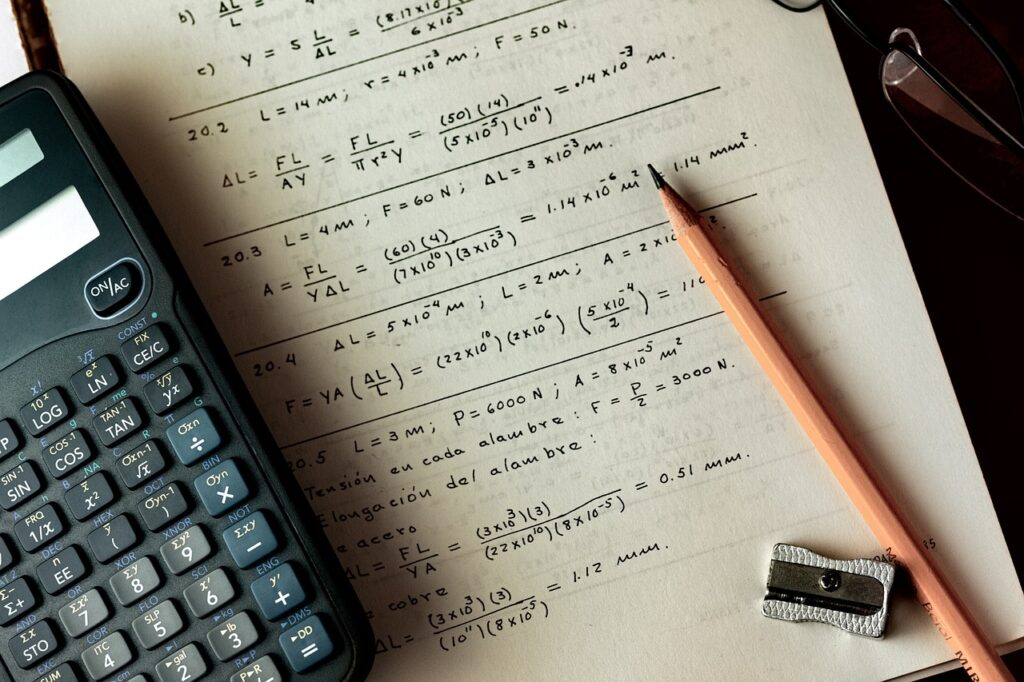
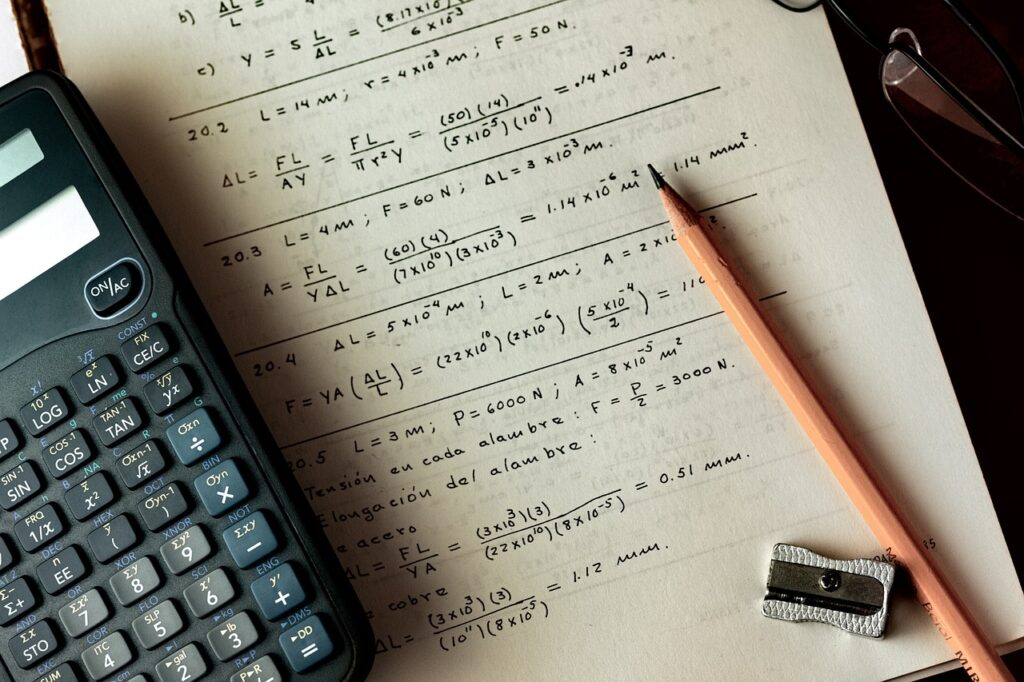
ここからは実際に試験を受けて見ての感想や実際に行った試験対策について解説していきます
まずは試験の概要について
・試験形式:パソコンによるCBT方式(全国260会場で受験可能
・試験時間:90分
・出題数:90問
・受験料:12,100円(税込み)
・出題範囲:公式テキスト+時事問題
1:救急医療の定義と概念
2:急変時の初期対応(BLS/ACLS)
3:症状別アセスメント
4:急性期におけるリーダーシップとチーム医療
5:家族支援と心理的ケア
6:災害時の対応
7:小児・高齢者の急性期ケアの特徴
8:医療制度や地域連携に関する知識
概要と出題範囲としては上記のようになっています
問題数90問、試験時間90分であること、出題範囲も広いことを加味すると、しっかりとした対策が必須です!
単純計算すると1問1分
公式のアプリ内の口コミの中には時間が足りないとのコメントも…
また終盤の10問くらいは状況設定問題です
読解に時間がかかるので、前半を早く解いて時間を確保しておくなど、コツがいります
以下では、試験対策など解説していきます
実際に試験を受けてみての感想
実際に問題を解いてみて思ったことは、問題が難しいというよりは、知識として知っているかいないか
要するに、勉強して知識として身についているかどうか
なので、いくら悩んでも解けないものは解けない
悩みすぎても正解にたどり着けないので、1分を目安に考えて回答に悩むようであれば、もっともらしいものを選択して、次に進んだほうが良いです!
救急など急性期の職場で働いていている方であれば、ある程度、知識や経験があるので、問題も解きやすいかと
しかし、問題の特性上、知識が求められるので、急性期での経験がない方・少ない方や、介護職、薬剤師さんなどは、それなりの勉強時間を確保しないといけない印象です
あと個人的に困ったのが、予想問題集に基礎編と応用編があり、模擬試験も2回分あり、何がなんで何を購入すれば良いのか分からなかったこと
結局、僕は公式問題集と予想問題集(基礎編)しか購入していませんが、実際に受験してみて思ったのは、これだけだと試験対策としては不十分だったなという印象です(なんとか合格はできましたが💦)
予想問題集(基礎編)のみでは、「あっ!この問題見たことある!」みたいな同様の問題が数問あったぐらい…
おそらく販売されているセットものを全て学習すれば、ある程度の問題はカバーされているんだろうなという印象
なので絶対に合格したい人は全ての教材が入ったコンプリートセットを購入することをおすすめします
ただ購入金額もバカにならないので、その人それぞれにあったものも紹介できたらとおもいます!
試験対策のポイント
上記の実際に試験を受けてみて思ったことを踏まえ、おすすめの勉強方法・試験対策をお伝えします!一つの参考までに!
まずは一通り公式テキストを読むこと。熟読するのではなく、あくまでもサクッと1周終わらせる!
予想問題集で実際に問題を解いてみて、問題の出し方や傾向を掴みます
解けなかった問題を公式テキストを見ながら復習
本番と同じ形式で出題されるので、少しでも出題形式に慣れておきたい人は必須
公式のアプリでも予想問題集を解くことが可能なので、通勤時間などのスキマ時間を活用
上記のSTEPを数回こなすことが重要です!
このSTEPを数回こなすことで試験対策としてはばっちりだと思います
このSTEPを踏まえて試験対策のポイントをまとめていきます
公式テキストの熟読が必須
問題は独特な言い回しが多いため、公式テキストはしっかり読み込んだほうが良く、過去問や模擬試験で慣れておくのがベストです
ただ学習する範囲が広いので、まずは自分の興味のある分野や職場で活かせそうな分野から始めてみるのもGOOD!
予想問題集を活用
予想問題集を使い知識の定着率の確認、かつ再学習
問題集を活用し、知識がついているか確認し、身についていない項目は公式テキストでも確認を行い確実なものにします!
今回、僕は公式テキストと予想問題集(基礎編)しか使用していませんが、応用編までやっておくべきだったなと反省…
基礎編のみでは、本番の試験で学習不足を感じました💦
模擬試験で本番の雰囲気に慣れる
本番と同じ形式で練習できるので、少しでも出題形式に慣れておきたい人は必須です
試験は90問90分なので、単純計算1問1分で回答する必要があります
かつ終盤の10問は状況設定問題なので1分で解くことは難しいことを加味すると最初の80問は1分以下で回答する必要があります
これらのことを考えると模擬試験で試験本番と同様の形式に慣れておくのがベストです!
公式アプリでスキマ時間を活用
公式アプリでも予想問題集を解くことが可能なので、通勤時間などのスキマ時間を活用して問題を解くことで効率よく学習を進めることが可能です
まとめ


急性期ケア専門士のメリット・デメリットについて、試験対策についてお伝えしてきました
ネットでこの資格に関して調べてみると、「意味がない」「自己研鑽」なんてワードも目にします
資格試験を受験することの意義を考えた時に、実際に働いている場で活かせないと意味がなかったり、受験するメリットないなと思いますが、受験をしてみての正直な感想は
もともと急性期で働いていても、知識の再整理という意味では意味があったと思います
バトンをつなぐという意味でも病院外での地域でのことなどに触れられたの良い学習機会でした
その他にも小児に関することや災害に関すること、急性期におけるリーダーシップなども学べるのは面白いところ
急性期に関する体系的なことを学ぶのであれば、良い機会になる資格だと思います
「急変に強くなる」ための土台を築くもの
もし急変現場で自信を持って働きたい、あるいは苦手意識を克服したいと考えているなら、非常に価値のある選択だと思います
何か皆さんの参考になるものであれば幸いです
最後までお読みいただきありがとうございました!