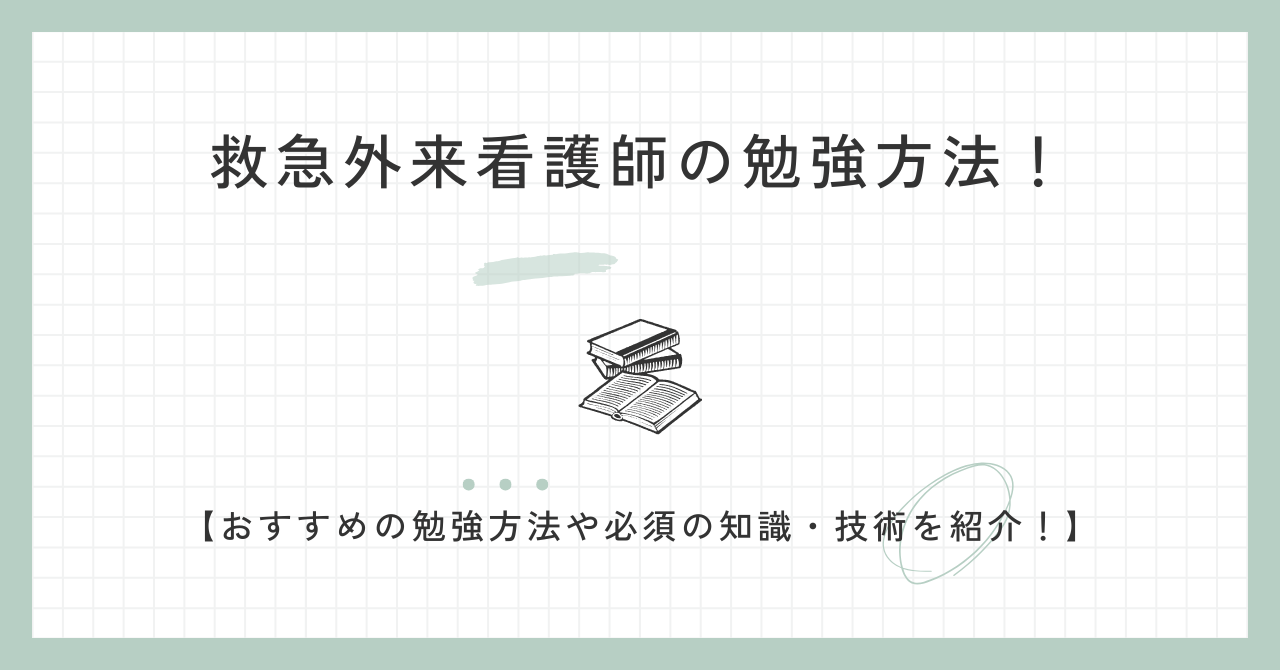今回は、「救急に配属になったけど何から勉強したらよいのかわからない」「おすすめの勉強方法を知りたい」「どんな知識や技術が必要になるのか知りたい」って人におすすめの記事です。
救急って聞くとただでさえ怖いイメージがあり、配属となれば自分が本当にやっていけるのだろうか、通用するのだろうかと何かと不安になるものです
また何から勉強し、どんな勉強したらよいのかわからず余計に不安が強くなることもあると思います
 すな
すな僕も救急外来で勤務をし始めた頃は、緊張しっぱなしで心臓バクバクでした💦
そこで今回はそのような不安が少しでも解消できるように、救急外来看護師の勉強方法をお伝えしていきます!
救急外来看護師におすすめの勉強方法


僕も救急外来で働き始めた頃は、その場所の雰囲気にすら緊張していました
外来で働くってだけで心臓バクバク💦
働き始めた頃の記憶を今でも鮮明に覚えています
今はバリバリ働いている先輩たちも、実は働き始めた頃はこんな思いをしながら働いていたんじゃないかと思います
ただでさえ緊張感がある場所で、ストレスフルな環境だと思うので、少しでもその環境になれるよう、おすすめの方法をお伝えしていきます!
おすすめの方法1:救急外来特有の流れを知る
救急外来の配属になった時に、まず最初に行ってほしいのが、勉強方法とは少し視点がずれるかもしれないけど、救急外来特有の流れを知るということ
救急外来は一般病棟と違って、最初に症状があって、そこから考えられる疾患を考えていきます
なので患者の訴えや症状から考え得る疾患を予測し、採血や画像など様々な検査を行います
救急車で患者が搬送されてきたときの流れを例にすると
例:胸痛の訴え、冷や汗、冷感あり→ACS(急性冠症候群)や大動脈解離、PEの可能性を考慮!
点滴、挿管、薬剤、DC、エコー、12誘導心電図、酸素など症状や疾患に合わせて準備!
まずはバイタルサイン測定を行いつつABCDの評価!症状観察!
バイタルを整えるために挿管やシースやCVの挿入が行われる
バイタルが落ち着いたら想定しうる疾患に応じた検査を進めていく
救急車で運ばれてきた際の、大まかな流れとしては上記のような形で進んでいきます
これを知りながら先輩の動きを見るだけでも、吸収力は上がり学習効率があがると思います!
おすすめの方法2:先輩の動きを意識して見る
次におすすめの方法ですが、先輩の動きを意識して見ることをおすすめします
配属になって最初から1人で全てを任されることはないと思うので、まずは見て覚えようとすること
最初に説明した救急外来特有の流れを意識しながら見ることで、より早く救急外来の環境に慣れることができると思います
流れを知り、今先輩は何をしているんだろう、何を準備しているんだろうと意識しながら動きを見ることは確実に自身のスキルアップに繋がります
対応した患者の振り返りを行う
救急外来では疾患名は同じであったとしても、同じ症例は二度とありません
なので同じ疾患であっても、必ずしも同じように行動すれば良いわけではないです
一つ一つの症例で優先順位や考え方は変わってきます
その中で先輩看護師のフォローがあるのであれば、症例を振り返り先輩看護師の考え方や優先順位の立て方を教えてもらうのは、とても良い勉強になると思います!
先輩の考え方を学び、自身の行動を見直し、次へとつなげていく意識が大切です!
救急看護師に必要な知識・技術


ここからは救急看護師に必要な知識や技術についてお話していきます
必要な知識
救急ではよく、幅広い知識が必要と聞いたり、イメージされている方も多いと思います
これは確かにそうだと思うけど、その中でも救急外来でよく遭遇する疾患や緊急度・重症度の高い疾患はある程度限られてきます
また、上記で救急外来特有の流れを知り、症状から想定される疾患を考える必要があることをお伝えしました。
症状から疾患を考える思考過程や疾患について学べるおすすめの書籍があるので紹介します
以下の2つをもっていれば、ある程度の知識はカバーできるので持っておくことをおすすめします!
必要な技術
救急外来特有の流れの中で、バイタルサインを安定化させることを説明しました
そのバイタルサインを安定させるのに必要な技術がたくさんあります
具体的には
- 気道確保や挿管介助
- CV(中心静脈カテーテル)挿入
- シース挿入
- 胸腔ドレーン
- 腰椎穿刺
などなど・・・
まだまだ必要な技術はたくさんあります
必要な技術に関してもおすすめの書籍があります!
必要な技術が網羅され、写真が豊富で場面をイメージしやすい構成となっているので、技術に不安がある方、知識を深めたい方におすすめです!
救急外来看護師におすすめの書籍をまとめた記事もありますので良ければ参考にしてみてください!


家族看護
救急では緊急度・重症度の高い患者が多く、患者のみではなく患者の家族も看護の対象です
救急で運ばれてくる患者家族の特徴としては、急な出来事のため衝撃を受け動揺される方が多いです
家族も看護の対象であることを知り、患者家族の心情を察し心に寄り添った対応することが救急の看護師には求められます
災害に関する知識
災害拠点病院で勤務されている方であれば、災害に関する知識は必ず必要です
普段生活していると忘れがちであり、災害に関することとなると辛いこともイメージされ、避けて通りたくもなります
しかし、これは救急で働く以上切っても切り離せないものでsy
近年は災害が発生する機会も増えており、いつ自分が被災するかもわかりません
救急で働く以上、災害発生時には必然的に対応しなければならないので、災害に対する知識は必須です
いつか起こるものと想定して準備しておくことが大切
今後MCLSという、「多数傷病者への対応標準化トレーニングコース」に参加することを考えているので、参加した際には記事にしてみたいと思います
救急看護師なら持っておきたい資格・受講しておくべきセミナー


救急の看護師であれば受講しておくべき資格やセミナーがいくつかあります
僕自身も受講しておすすめのものがありますので、参考いただけると幸いです
BLS
これは言うまでもないかもしれまんせんが、医療職者であれば受講すべきものだと思います
BLSとは、Basic Life Supportの略称で、心肺停止または呼吸停止に対する一時救命処置のことです
救急外来で働く以上、心肺停止の患者に会わないことはないと思うので、必須の知識です
ACLS
BLSの続いて必須の知識がACLSです
ACLSとは、Advanced Cardiovascular Life Supportの略称で二次心肺蘇生法のことです
日本ACLS協会によると以下のように説明されています
病院等医療施設において医師を含む医療従事者のチームによって行われる心配蘇生法であり、基本はCPR(気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ)と共に、気管挿管などの確実な気道確保と高濃度酸素投与、電気除細動、静脈路確保と薬物投与を主体とした手技によりなされる高度な処置
救急や循環器を専門とする領域で働く場合は、必要不可欠な知識・技術です
心室細動、無脈性心室頻拍、心静止、PEAへの対処方法、徐脈および頻脈への対応、急性冠症候群、急性虚血性脳卒中などの二次救命処置法を学ぶことができます
JNTEC
これも救急の看護師であれば受講しておくべきセミナーです
外傷に対する看護が学べるセミナーで、外傷に対する知識や技術、看護を学ぶことができます
外傷に特化したセミナーではありますが、ショックに対する考え方など外傷以外にも応用することができる知識を学べます
外傷に関して学べ、その他にも応用することができる知識も学ぶことができたので、個人的には本当に受講してよかったおすすめのセミナーです
受講するしないに限らず、このガイドラインは持っておくべき1冊!
JNTECについて詳しく解説した記事がありますので、気になる方は参考にしてみてください!
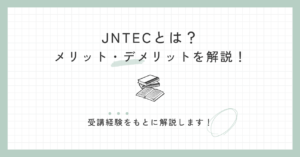
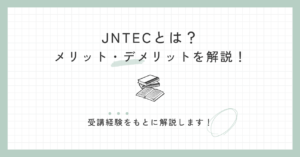
その他にも、救急看護師であれば受講しておくべき資格やセミナーについて詳しく解説した記事がありますので、こちらも良ければ参考にしてみてください


まとめ


救急外来看護師におすすめの勉強方法について説明してきました!
おすすめの勉強方法としては、1.救急外来特有の流れを知ること、2.先輩の動きを意識して見る、3.対応した患者の振り返りを行う、の3つです
上記の3つを意識して行動することで、より早く救急外来の環境に慣れると思います
救急外来に配属になると、さまざまな不安や緊張に襲われると思います
今回の記事の内容や紹介した本を参考に、少しでも皆様の不安や緊張を和らげることができ救急外来の環境に慣れるためのお手伝いができたのであれば幸いです
下記の記事も参考にして頂けると幸いです!