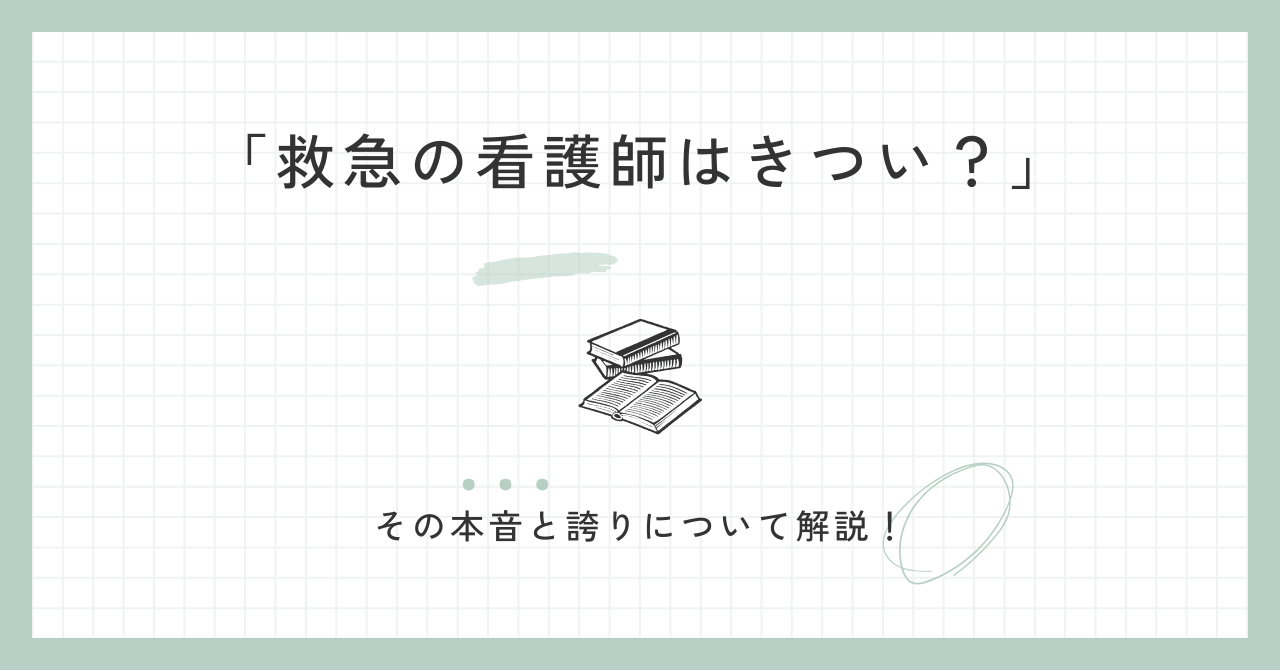「救急はきつい」 「ICUはメンタルが削られる」
こんな声を耳にすることは少なくありません…
確かに救急・集中治療の現場は忙しく、責任も重く、緊張感の連続です
でも、その厳しさの中には、他の領域では得難いやりがいや専門性があります
「きつい」と言われる理由を紐解きながら、それでも多くの看護師がこの領域に情熱を注ぐ理由をお伝えします!
 すな
すな今までの経験をもとに、「きつい」と言われる理由を解説します!
救急・ICUがきついと言われる理由


救急やICUがなぜ「きつい」と言われるの解説していきます
理由としては以下のようなものがあります
1:瞬間の判断力が求めらる
救急やICUで働いていると、急変や容態の変化しやすい患者にあたることは多いと思います
そのような時は秒単位での判断を求められることがあります
常に命を預かる緊張感
急変時には瞬間の判断を求められますが、その他には、バイタルサインや症状から医師に報告すべきことなのかなど、瞬時の判断は必要ないにせよ、何かと判断をしなければならない場面は多々あります
2:業務量の多さと情報量の密度
一人の患者に対する情報量が多く、状態変化に応じた対応が求められます
僕はICU、救急病棟、救急外来を行き来していますが、救急病棟と比較すると、救急外来やICUでは一人の患者に対する業務量は段違いに多いです
状態が不安定な患者は、バイタルサインや症状が常に変化するため観察・アセスメントは重要です
都度変化に合わせて処置や薬剤投与が行われるため業務量は必然的に多くなります
3:精神的な負担が大きい
救急外来・ICUで働いていると重症患者の対応をするので、常に命を預かっている緊迫感があります
また、事故による四肢の損傷、脊損、死別など、患者本人や家族の悲痛な思いを今までにたくさん見てきましたが、精神的なタフさが必要です
そして、いかにそこに看護師として精神的・スピリチュアル的な介入ができるかが大切なんじゃないかと感じています
個人的な意見ですが看護師の一言で救われる方もいると信じています
介入することで、患者・家族が精神的にもスピリチュアル的にも救われるような看護をしたいなと思います
4:身体的な負担が大きい
救急外来では常に救急車の対応をする必要があります
救急車がひっきりなしに来る場合は常に動きっぱなしです
ICUでは患者のケアや処置介助、薬剤の準備から投与など何かと動きっぱなしです
一日を通して休憩以外座れない日は普通にあります
身体的な負担が大きいのは救急・ICUに限った話ではないと思いますが、常に全力なので疲れるのも事実です
身体的な負荷が大きので個人的には体調管理にはかなり気を使っています
体調管理を意識するようになってから、健康になった実感があるし、連勤でもしんどくなくなった実感があります
連勤を楽にする方法の記事も書いていますので、よければ参考にしてみてください!


5:多職種連携のスピード感
救急外来や、特にICUでは医師・薬剤師・臨床工学技士などとの連携を瞬時に行う必要があります
特に医師との連携は必須であり、これから行われる処置や薬剤投与に関しては共通認識を持ち意思疎通が図れることが大切です
6:研修や勉強会が多い
救急で働いていると、専門性を高めるために様々な研修や勉強会に参加することが求められます
具体的にはJNTECやJPTEC、ICLS、ACLSなどなど・・・救急に関する研修はあげればかなりの数の研修があります
その他にも救急外来ではいろんな患者が来院するため、いろんな科のさまざまな疾患に対する知識が必要です
不足している知識は自己学習で補う必要があります
救急で働くには、いろんな科に対応できる幅広い知識が求められつつ、専門性を高めることが求められます
救急で働く看護師には積極的にスキルアップを目指し、そのためには休日を使って院内外の研修や勉強会に参加することが必要です
いかに時間を確保して、自己研鑽を進めていくかが大切になってきます




それでも救急看護に惹かれる理由


上記では救急やICUが「きつい」と言われる理由について説明をしてきました
ここからは、それでも救急看護に惹かれる理由について説明していきます
1:命に直結する介入ができる
大げさな言い方だとは思いますが、ICUでの自分のケアが患者の回復に直結したり、救急外来での対応で患者の命を救うことができたと思うとやりがいを感じます
2:専門性が高く、スキルが磨かれる
急変対応、呼吸・循環管理など高度な知識と技術が身につきます
これは勉強や研修などをやらなければならない反面だと思いますが、知識・技術が身に付きスキルの向上を実感するときは、頑張ってきて良かったと思えるものです
急変対応には苦手意識を持たず行えるし、呼吸循環に関しても勉強して強くなったなと実感しています
3:チームでの達成が大きい
多職種や看護師との連携で乗り切る場面が多く、絆が深まります
救急外来やICUでの急変時などは、チーム全員で取り組む必要があり、救命できた時の達成感は大きなものです
特にヘリでは医師1名、看護師1名での活動となるため、その達成感はより大きなものです!
4:キャリアの広がり
急性期での経験は、今後の看護師人生において大きな強みとなる可能性があります
よく「救急で働いてたんだから、どこでもやっていけるでしょ」なんて言葉を耳にしますが実際はどうなのか…
今後転職を考えているので、実際に救急での経験が活かせたのか実際にどうだったのか、詳しくお話ができるんじゃないかと思っています
5:現場の実際の声を紹介
実際に救急の現場での声を紹介します
確かに辛い瞬間もある。でも、この患者さんICUに来たときにこんな状態だったのに、退院されたって思えたとき、やっててよかったと思う。
その他にも
毎日が刺激的で、自分が試されている感じ。救急の看護師でいられることに誇りを持っています。
きつさへの対処法
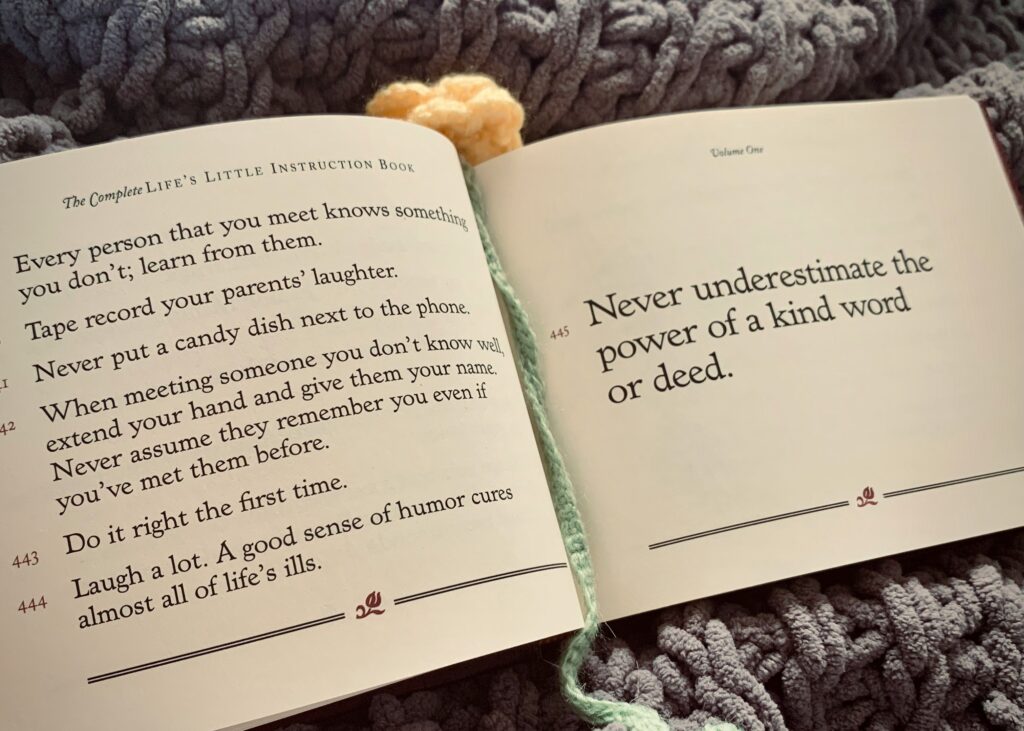
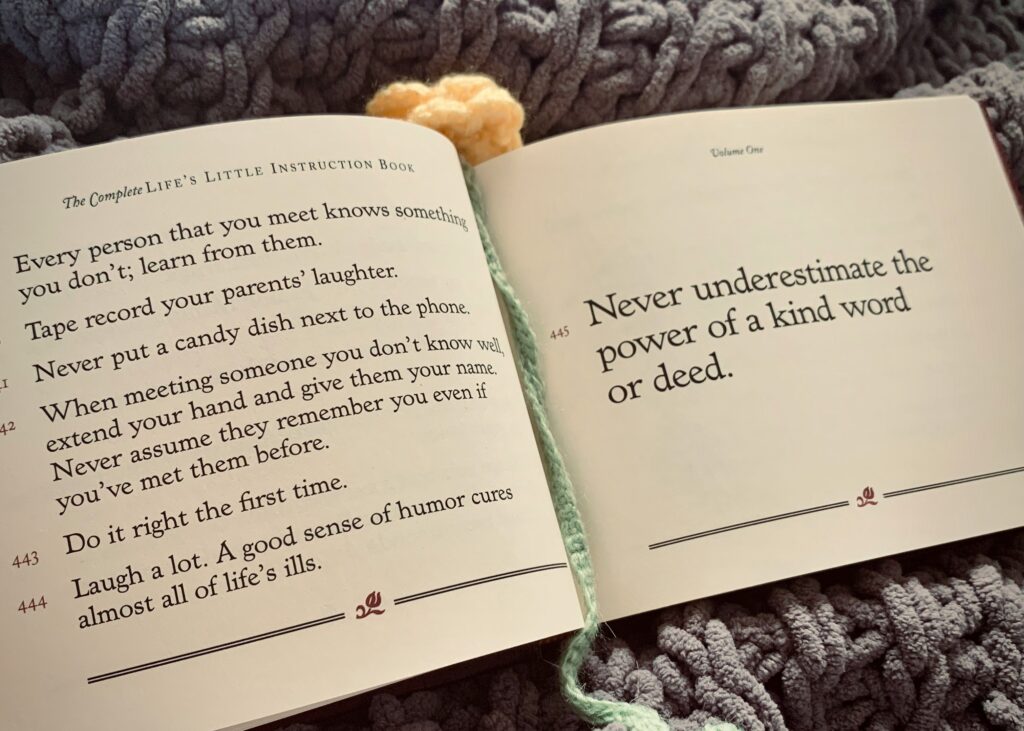
救急やICUでのやりがいや魅力が理解でき、働き続けたい思いがあるなら、きつさに対して適切に対処する必要があります
ここから、そのきつさに対する対処法をいくつか紹介します
1:休日は休む
仕事と休みをきっちり分けることも時には大切です
「勉強をしなければ置いて行かれる、また怒られる…」
このような気持ちはものすごくわかります
しかし、昔の僕はこの「やらなければならない」という思いでいっぱいで、休みの日も仕事のことを考えて疲れが取れない、それどころか余計にストレスを貯めるという悪循環に陥っていました
休日にも勉強して少しでも知識不足を補わないという思いはわかりますが、休むときはしっかりと休み気分転換をするほうが結果的には上手くいきます
勉強をするときは勉強し、休むときは休む
このメリハリが大切だと思います!


2:学習は計画的に
救急・ICUで上手くやっていくには、やはりスキルアップは求められるもので、これをストレスと感じずに上手くやることが大切です
なので、休む時には休むと言った後ですが、時には休日を使って学習を進めていくことも必要です
僕は看護師の夜勤があることをメリットとして捉え、夜勤前の夜中に効率よく学習するようにしています
人それぞれでリズムがあると思うので、リズムに合わせて計画的に学習を進めていくのが良いかと思います


3:相談する
長年救急で働いていると、数年おきにメンタル的にしんどくなることがあります
少しでも、しんどい・きついと感じたら、まずは信頼できる上司や同期、友人に相談するのも一つの手です
感情を表に出すだけでも気持ちが楽になるものです
上司や同期にも同じような経験があれば、良いアドバイスをくれることもあります
まとめ


救急やICUで働くことには、身体的にも精神的にも「きつい」と感じる場面は多々あります
しかし、それは看護の本質に深く関わる領域でもあります
「きつい」からころ得られる喜びも、誇りもあります
命に寄り添い、回復の一歩を支える‐それが救急看護の真髄です
「きつい」だけでは語りつくせない救急の魅力、あなたも見つけてみませんか?
この記事が「救急ってしんどいだけじゃないんだ」と思ってもらえるきっかけになれば嬉しいです!
あなたの選択に、すこしでも役立つものになりますように!